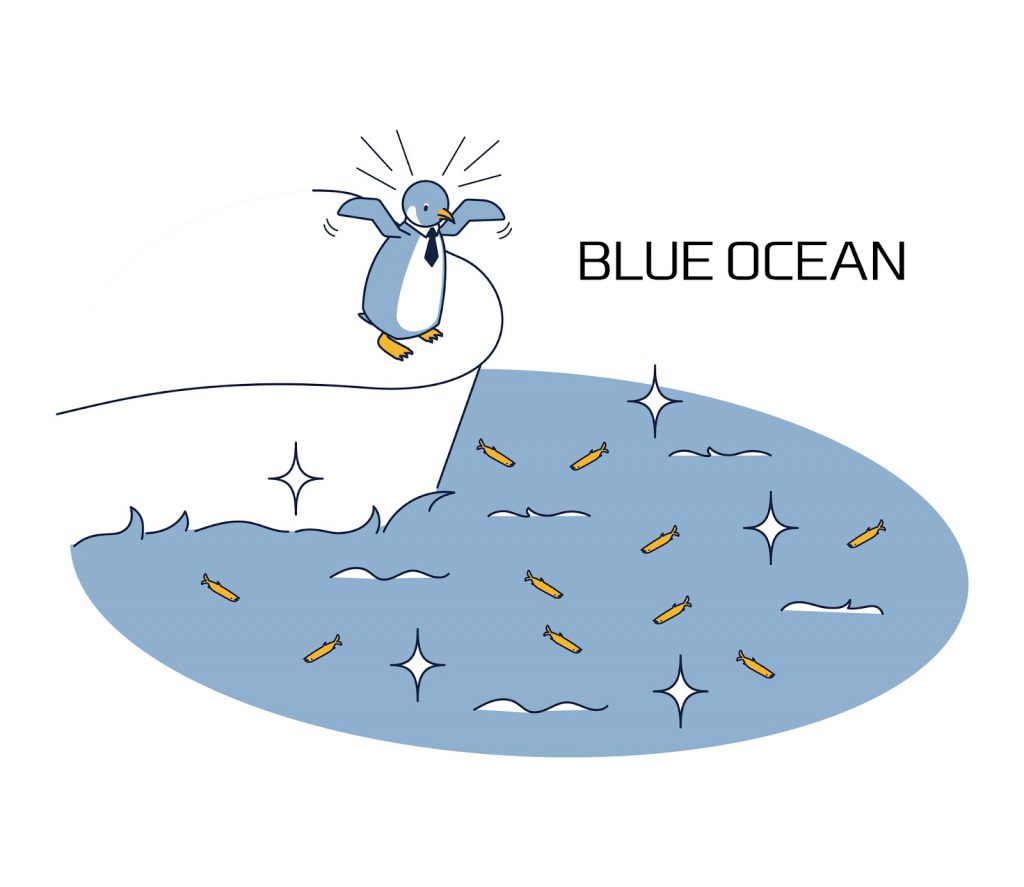「自社に強みがあるのか、正直、自信がない」
「競合と差別化できるところが何なのか、わからない」
このように悩む方は、非常に多いです。
自社の強みを見つけるには、意識的に取り組む必要があります。
この記事では、“マーケティングの祖父”ことピーター・F・ドラッカーの金言を借りながら、企業の強みを見つけるための考え方・見つけ方のヒントをお伝えします。
自社の強みを見つけることは、事業を継続するために欠かせないことです。
事業の定義は3つの要素からなる。第一は、組織をとりまく環境である。(中略)第二は、組織の使命すなわち目的である。(中略)第三は、そのような使命を達成するために必要な強みについての前提である。
『チェンジ・リーダーの条件』
ドラッカー教授は、その事業が有効かどうかを判断する基準を、上記のように示しています。
第一に、組織を取り巻く環境。それは「社会とその構造、市場と顧客、そして技術の動向」であると指摘しています。
第二に、事業の目的の整合性です。組織の目的に、事業の目的が一致しているかどうか。その組織ならではの役割を通じて社会に貢献し、ふさわしい成果を得ているか、常に問い続ける必要があります。
そして第三に、以上の二つを満たしたうえで、「それはわれわれの強みを基盤としているか」を問わなければなりません。
事業の成果は、機会を得るのみならず、強みを発揮しなければ生まれません。
組織をとりまく外部環境(社会とその構造、市場と顧客、そして技術の動向)に対し、保有する知識群を使って価値を提供できてはじめて、その事業は有効な事業として成立します。
この記事では、経営学で定番の「SWOT分析」などはあえて紹介しません。
この記事では、もっと本質的で、定性的な領域で、あなたの会社の強みを見つけられるヒントをお伝えすることが目的だからです。
ぜひあなたも、ドラッカー教授の思考を参考に、自社の強みを再発見してみてくださいね。
目次
強みとは「知識」である
事業が成功するには、知識が、顧客の満足と価値において、意味あるものでなければならない。(中略)知識は、事業の外部、すなわち顧客、市場、最終用途に貢献して初めて有効となる。
『創造する経営者』
ドラッカー教授は、著書『創造する経営者』で、こんな事例を紹介しています。
ある大企業の事業部は、世界中の金属加工工場と同じ機械と工程によって、無数のパターンの金属片を切削し、屈曲させ、製品をつくっていました。
顧客が欲しいものを説明し終わらないうちに見本をつくり、すぐさま出荷を開始でき、値段も顧客の予算の半値程度で提案することができたといいます。
実はこのサービスは、他の事業部よりも利益率がかなり高かったのです。
なぜなのでしょう?
この事業部は、【顧客にとっての価値は「時間」である】と定義していました。ここにおいて「卓越した知識」は、設計の単純さ、蓄積された見本作製ノウハウだったのです。
この事例に対してドラッカー教授は「平凡なことを非凡に行う」と表現しました。
顧客に貢献可能な「知識」をつかって、顧客価値を実現していく力。それこそが組織の「強み」なのです。
ここで重要な観点があります。
それは、「自社の強みは何か」という問いかけが先行するのではなく、「顧客にとっての価値は何か」からスタートしなければならないということです。
「われわれの事業は何か」に答えを出すには、「われわれの顧客は誰か。どこにいるか。彼らにとっての価値は何か」を考えなければならない。事業を決めるものは世の中への貢献である。貢献以外のものは成果ではない。
『マネジメント』より
強みとなる知識は「製品を生み出す仕組み」のなかにある
経済的な業績は、差別化の結果である。差別化の源泉、および事業存続と成長の源泉は、企業の中の人たちが保有する独自の知識である。成功している企業には、常に、少なくとも一つは際立った知識がある。そしてまったく同じ知識をもつ企業は存在しない。
『創造する経営者』
差別化は、顧客に選ばれる理由、支持される理由となる、重要なバロメーターです。事業が長期的に利益を獲得するには、長期にわたる差別化要因が必要です。それが強みの基盤となります。
差別化の源泉は、企業独自の知識にあります。
その知識は、製品・サービスや仕組みとして体現されているはずです。
表面的には製品やサービスといった、“目に見える部分”で差別化がはかられているようにも思われますが、本質的な差別化の要因は、製品やサービスを生み出す仕組み・プロセスにあります。
仕組み・プロセスは、外部からはわかりづらく、形だけ真似てもうまくいきません。組織の経験の蓄積だからです。いわば“組織文化”が、独自の仕組み・プロセスをもたらしているわけですね。
- あなたの組織の、製品・サービスを生み出す仕組みには、どんな独自性がありますか?
- そこで際立っている知識は何ですか?
この問いに、企業の強みを見つけるヒントが隠れています。
知識とは行動の結果である
事業の定義と密接に関連するものとして、卓越性の定義がある。卓越性とは、常に知識に関わる卓越性である。すなわち、事業にリーダーシップを与える何らかのことを行いうる人間能力のことである。事業の卓越性を明らかにするということは、その事業にとって真に重要な活動が何であり、何でなければならないかを決定することである。
『創造する経営者』より
知識とは、机上のものではなく、人間が行動した結果、得られるものです。
言い換えれば、失敗と成功の経験の蓄積です。
たとえば飲食店の仕入れ担当者は、新鮮な食材を仕入れる知識をもっています。
ホール担当者が、本日のおすすめをどのようなタイミングでどのように勧めると、気前よく注文してくれるか熟知していれば、顧客満足と利益をたくさん生み出してくれることでしょう。
一人ひとりの人間の能力が共有され、蓄積されると、組織の知識・強みとなり、それが卓越性を実現します。
知識が行動の結果である……ということは、どのような活動・どのような行動を増やせば、より卓越するのかを、組織のメンバー全員で考えることが重要となります。
- あなたの組織で真に重要な活動とは何ですか?
- そのためにどんな活動を増やしますか?
- そのためにどんな活動を減らしますか?
- そのためにどんな活動を新たに始めるべきですか?
集中なくして強みの発揮なし!
事業の定義は、集中を強いるものでなければならない。卓越性を獲得すべき知識を特定し、リーダーシップを獲得すべき市場を特定しなければならない。
『創造する経営者』より
「成果をあげる秘訣を一つだけ挙げるとすれば、それは集中である」とドラッカー教授は言いました。
集中とは、「どこに」「どれだけ」という2要素で成り立っています。
市場でリーダーシップを獲得できているかどうかは、本当にその知識が顧客に貢献しているかを見極める重要な判断材料です。
仮にリーダーシップを獲得できていない場合、問題の所在を明らかにしなければ、事業があっという間に陳腐化してしまいます。
- 強みとなる自社の卓越した知識は、本当に現在の事業と関係しているのか?
- その事業が継続的な顧客との関係性を深められているのか?
ドラッカー教授は「いかなる企業も、多くの知識において同時に卓越することはできない」「一つの領域において卓越しなければならない」と、集中の大切さを説いています。
時代の変化に合わせて強みを磨く
イノベーションは強みを基盤としなければならない。イノベーションに成功する者はあらゆる機会を検討する。自分たちに最も適した機会はどれか、自分たちの組織に適した機会はどれか、自分たちが得意とし実績のある能力を生かしてくれる機会はどれかを考える。
『イノベーションと企業家精神』より
イノベーションは強みと大いに関係しています。企業の強みに関係しないイノベーションはたいてい失敗します。
とはいえ、企業の強みは変わっていくものです。自らの組織の卓越性を再定義し、さらに磨きをかけて事業の多角化を成し遂げることを推進していくべきものです。
たとえばコピー機でよく知られるキャノンは、創業1937年~1967年までは、カメラの事業が中心でした。ライカとライバルだったのです。
ところが高度経済成長期に突入すると、キャノンは「右手にカメラ、左手に事務機」と多角化を宣言しました。
キャノンは自社の保有している卓越した知識を電卓・トナー・インク・ファクシミリにまで拡張し、時代の変化に適合していったのです。
自社の知識や強みを棚卸しよう
自社の知識を把握するための知識分析の最善の方法は、自社が成功してきたものと失敗してきたものを調べることである。
『創造する経営者』より
そもそも、自社の知識のなかで、卓越したものを、どうやって見極めることができるのでしょうか。
ポイントは2つあります。
①これまでの成功と失敗を徹底的に調べる
強みは過去の経験値です。なればこそ、過去にヒントがあるはずです。
10年くらいの長期的な視点で、繰り返されてきた成功と失敗を整理してみましょう。
②外部の者に強みを聞く
自分たちが当たり前だと思っていたことが、実は第三者から見ると、競合にはない強みだった……これは大企業から中小企業まで例外なく、よくある話です。
逆のパターンもあります。
自分たちが強みだと信じていたことが、他者がいともたやすくできてしまうことだった。……なんてことも、よくあります。この場合、それは自社にとって弱みとなるでしょう。
まとめ
本稿では、“マーケティングの祖父”ことピーター・F・ドラッカー教授の洞察を紐解きながら、企業の強みを見つけ、それを事業成長に繋げるための重要な考え方と具体的なヒントを探ってきました。
ドラッカー教授が示すように、事業の有効性は、組織を取り巻く環境への適応、使命との整合性、そして何よりも「強みを基盤としているか」という問いによって判断されます。強みとは、顧客にとっての価値を生み出す「知識」であり、それは単なる製品やサービスだけでなく、それらを生み出す独自の仕組みやプロセス、そして組織に蓄積された経験と人間能力の中に宿っています。
自社の強みを見つけるためには、「顧客にとっての価値は何か」という視点を起点とし、外部環境の変化を捉えながら、自社が持つ独自の知識や能力を棚卸しすることが不可欠です。過去の成功と失敗を徹底的に分析し、外部の意見にも耳を傾けることで、自社が本当に秀でている領域、すなわち「平凡なことを非凡に行う力」を発見できるはずです。
そして、強みは決して静的なものではありません。時代の変化に合わせて自社の卓越性を再定義し、磨き続けることで、事業の多角化や新たな価値創造へと繋げることができます。集中すべき領域を見極め、強みを活かせる機会に積極的に挑戦していく姿勢こそが、持続的な事業成長を実現するための鍵となるでしょう。
この記事が、皆様の企業が持つ独自の強みを再発見し、それを活かした事業展開を進めるための一助となれば幸いです。

 お気に入りに追加
お気に入りに追加Dラボ
当サイトDラボを運営しております。
ドラッカーを学んだ経営者やビジネスマンが実際に仕事や経営に活かして数々のピンチを乗り越え、成功を収めた実例を記事形式で紹介しています。
また、「実践するマネジメント読書会」という、マネジメントを実践的に学び、そして実際の仕事で活かすことを目的とした読書会も行っております。
2003年3月から始まって、これまでに全国で20箇所、計1000回以上開催しており、多くの方にビジネスの場での成果を実感していただいています。
マネジメントを真剣に学んでみたいという方は、ぜひ一度無料体験にご参加ください。
最新記事 by Dラボ (全て見る)
- 【ドラッカーに学ぶ】マネジャーの役割と仕事は?必要なスキル4選を解説。 - 2025年3月26日
- 【ドラッカー流!チーム作りの極意】成果を出す組織が実践するマネジメントの基本。 - 2025年3月20日
- 企業の強みとは何なのか?競合にはない強みの見つけ方とは。 - 2025年3月5日
- なぜ自分の部下は成長しない?上司として伝えたい成長の秘訣7つを徹底解説。 - 2025年2月19日
- 正しい部下の育て方はある?自己成長を促すために必要な7つのポイントを徹底解説。 - 2025年2月5日
 Facebook
Facebook