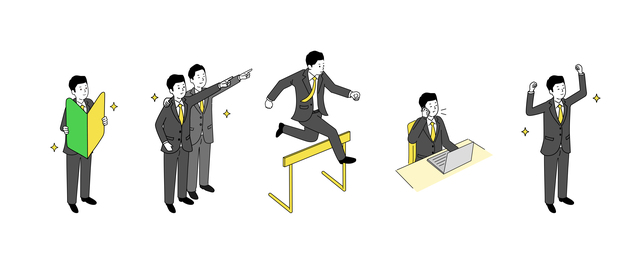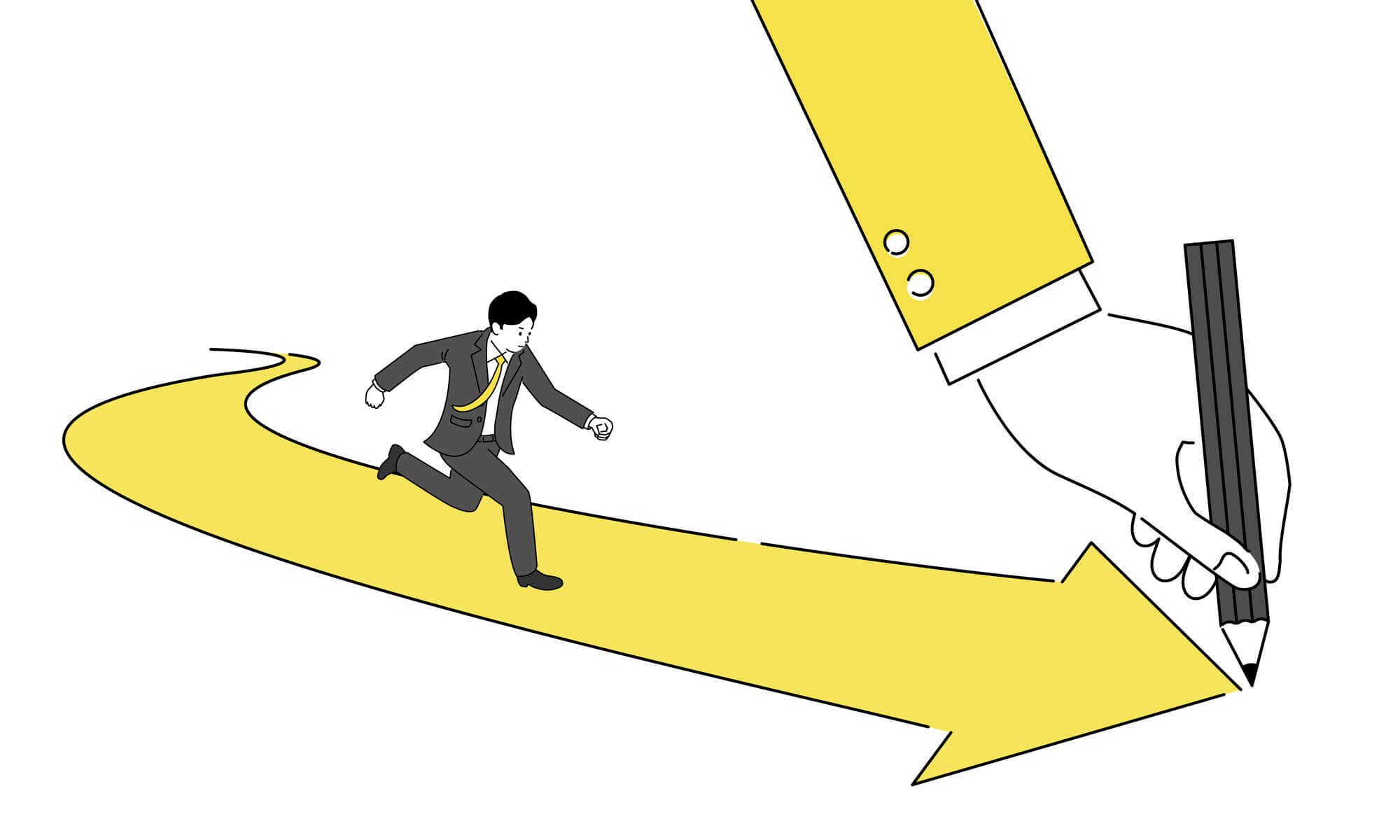現代のビジネスシーンにおいて、組織を率い、成果を最大化するマネジャーの存在は不可欠です。
しかし、単に指示を出すだけでなく、チームを成功に導くためには、どのような役割を担い、どのような仕事に取り組むべきなのでしょうか?
本稿では、マネジメントの巨匠、ピーター・F・ドラッカーの洞察を基に、「マネジャーとは何か」という根源的な問いから、成果を上げるために不可欠な5つのポイント、そしてマネジャーが磨くべき4つの重要なスキルを明らかにしていきます。
ドラッカー流のマネジメントの本質を理解し、あなた自身のリーダーシップをさらに高めるための一歩を踏み出しましょう。
目次
そもそもマネジャーとは何か
マネジャーをマネジャーたらしめるものは、成果への貢献という責務である。
『マネジメント(エッセンシャル版)』より
ドラッカー教授は、マネジャーとは、「命令する権限」を有する者ではなく、「貢献する責任」を持つ者だといいます。
それゆえに、組織における「マネジャー」と「専門家」の違いは次のように区別されます。
| 専門家 | 自身の知識や情報をアウトプットして、他者に有益なインプットをもたらす。 |
| マネジャー | 専門家の知識や情報を組織全体の成果に結びつける。 |
たとえばWEBコーダーは、WebサイトのHTMLやCSS、JavaScriptなどのプログラミングに関する知識や情報をアウトプットすることで、仕事を行います。まさに専門家です。
一方でWEB事業部のマネジャーは、WEBコーダーやWEBデザイナーの専門家たちを率いて、チーム全体が成果をあげられるように仕事を行います。
オーケストラで例えるとわかりやすいです。WEBコーダーとWEB事業部のマネジャーは、「楽器奏者」(専門家)と「指揮者」(マネジャー)の関係といえるでしょう。
マネジャーの役割は2つある
ドラッカー教授は、マネジャーの役割について、次のように言及しています。
①第一の役割は、部分の和よりも大きな全体、すなわち投入した資源の総和よりも大きなものを生み出す生産体を創造することである。
(中略)
②第二の役割は、そのあらゆる決定と行動において、ただちに必要とされているものと遠い将来に必要とされるものを調和させていくことである。
『マネジメント(エッセンシャル版)』より
第一の役割:部分の和よりも大きな全体を創造する
単なる足し算ではなく、メンバーそれぞれの強みを生かして、チームの総和を増やす。それが、マネジャーの第一の役割です。
まさにオーケストラ。実際ドラッカー教授は、部分の和よりも大きな全体を生み出すマネジャーを、オーケストラの指揮者に例えました。
一人ひとりの演奏者の強みを最大限に引き出すことで、全体で一人ひとりの弱みを意味のないものにし、結果的にチームが大きな成果をあげる。これが指揮者(≒マネジャー)の役割なのです。
第二の役割:長期・短期の視野でバランスのとれた意思決定を行う
マネジャーたるもの、いま目の前にある成果を追うのはもちろんのことですが、長期的な視野にたち、事業の方向性や人材育成に意識を向けなければなりません。
たとえば人材育成に関して、ドラッカー教授は、「近視眼的に人を育ててはならない」といいます。
身につけさせるべきスキルはある。だが人を育てるということはそれ以上のことである。キャリアと人生に関わることである。仕事は人生の目標に合わせなければならない。
『非営利組織の経営』より
長期的に考えるとは、たとえば次のような問いかけのことです。
- いま行っていることは、全体にどのように役立っているか
- 全体から考えて、いまやるべきことは何か
- いま行っていることは、長期の成果にどのように結びついているのか
- 長期の視点から見て、いまやるべきことは何か
マネジャーは常に、「全体と部分」という空間軸、「長期と短期」という時間軸を念頭に置きながら仕事をする思考習慣を身につけなければなりません。
マネジャーの仕事
あらゆるマネジャーに共通の仕事は五つである。①目標を設定する。②組織する。③動機付けとコミュニケーションを図る。④評価測定をする。⑤人材を開発する。
『マネジメント(エッセンシャル版)』より
マネジャーは、チームを率いて、一人ひとりの貢献を、組織全体の成果に結びつける役割があります。
オーケストラに言い換えるならば、楽器奏者たちの奏でるメロディーを、全体の美しいハーモニーとなるように導く指揮者。それがマネジャーです。
そのなかでもとくに重要な3点は、マネジメントにおけるPDCAサイクル、いわば“マネジメントサイクル”を繰り返すために不可欠な要素です。
その3つについて、以下に整理してみましょう。
▶目標を設定する
まずはじめにチームの目標を示すことが、マネジャーの大切な仕事です。
組織全体の目標から導き出されたチームの到達点。それが目標です。
チームが目標を達成し、組織全体の成果に貢献するためには、仕事を客観的に設計し、適切に人材を配置し、仕事を組織化する必要があります。それがマネジャーの仕事です。
▶動機付けを行う
働く人たちがイキイキと働き、組織のなかで自己実現を図りながら、みずから成長する。それこそが真の人材開発です。ここで必要なのは、マネジャーのコミュニケーションスキルです。
▶目標到達度のフィードバックを行う
チームの成果は、必ず測定し、組織全体の目標に対してどれだけ到達しているか、マネジャーが評価・フィードバックしなければなりません。
何をどれだけ達成しているのか?
これを客観的に評価するヤードスティック(尺度)を定義する必要があります。
マネジャーに不可欠な4つのスキル
成果をあげるチームづくりのためには、メンバーを正しく方向付ける必要があります。
そのためには、マネジャーとして不可欠なスキルがいくつかあります。以下に、その一部を領域に分けてご紹介します。
スキル①意思決定
ドラッカー教授は、意思決定を「見解」から始め、徹底的な検討と実行によって成果に繋げるプロセスとして捉えています。
問題の明確化:本質を見抜く洞察力
意思決定の出発点は、問題に対する多様な「見解」を理解することです。異なる意見を奨励し、それぞれの妥当性を深く検討させることで、意思決定の土台を築きます。
何についての決定なのかを明確にするには、表面的な事象に惑わされず、問題の本質を見抜く洞察力が求められます。
ドラッカー教授は警鐘を鳴らします。「間違った問題に対する正しい答えほど、実りがないだけでなく害を与えるものはない」と。
意見の対立の奨励:多様な視点を取り込む
「意見の対立を見ないときには決定を行わない」。これはドラッカー教授が提唱する意思決定の第一原則です。
「満場一致」は理想的に見えますが、教授はむしろ危険な兆候だと指摘します。
成果を上げるマネジャーは、意図的に意見の不一致を生み出すことで、表面的にはもっともらしくても誤った意見や、不完全な情報による判断ミスを防ぐのです。
意見の相違の重視:異なる現実を理解する
「自分は正しく、彼は間違っている」という前提で議論を始めてはなりません。
意見の不一致の原因を必ず突き止めようとする姿勢が重要です。異なる意見を持つ者は、多くの場合、自分とは異なる「現実」を見ています。
その違いにこそ、新たな発見や気づきの機会が潜んでいるのです。意見の相違を尊重し、その背景にある現実を理解しようと努めましょう。
行動の必要性の判断:安易な決定を避ける
すべての状況に意思決定が必要なわけではありません。
ドラッカー教授は、意思決定を「外科手術」に例え、慎重な判断を求めます。
意思決定とはシステムへの干渉であり、ショックのリスクを伴う意思決定は、良い外科医が不要な手術を避けるように、安易に行うべきではありません。行動すべきか否かを見極めることも、マネジャーの重要なスキルです。
意思決定の実行:行動と成果へのコミットメント
効果的な意思決定は、単なる結論ではなく、行動と成果への明確なコミットメントを伴います。
決定を行った後も、
- 「誰がその決定を知る必要があるのか」
- 「取るべき具体的な行動は何か」
- 「なぜその行動が必要なのか」
- 「行動を起こす人が実行できるように、その行動はどのようなものであるべきか」
といった問いを自らに投げかけ、実行を徹底的にフォローアップする必要があります。
フィードバックの仕組み化:継続的な改善
意思決定を実行した後、その状況が実際にどうなったのかを検証する仕組みを構築しましょう。
多くの場合、現実は想定通りには進みません。
最善の意思決定でさえ、予期せぬ障害に直面し、時間とともに陳腐化していきます。したがって、実行の成果から継続的にフィードバックを得て、改善を繰り返すことが、期待する成果を手に入れ続けるための鍵となります。
スキル②コミュニケーション
ドラッカー教授は、効果的なコミュニケーションには「4つの原理」が存在すると説きます。
原理(1):コミュニケーションは「受け手」の知覚である
コミュニケーションが成立するかどうかは、話し手ではなく「受け手」によって決まります。
大哲学者ソクラテスが言うように「大工と話すときは、大工の言葉を使え」です。
自分の話が相手に正しく伝わるためには、受け手の知覚能力に注意深く関心を払い、相手の理解できる言葉で語りかける必要があります。
原理(2):コミュニケーションは「期待」である
人間は、自分が期待していることしか知覚しない生き物です。
受け手が予期していない情報は聞き流されるか、反発を受ける可能性が高いと心得ましょう。
したがって、話し手はまず、受け手が何を期待しているのかを理解することから始める必要があります。
原理(3):コミュニケーションは「要求」である
最終的に、コミュニケーションは受け手に何らかの行動や理解を求めることになります。
その要求が受け手の価値観、欲求、目的に合致したとき、コミュニケーションは強力な力を発揮します。しかし、合致しない場合は抵抗を受けるのが人間の心理です。
原理(4):コミュニケーションは「情報」ではない
コミュニケーションは、感情、価値観、期待、知覚といった要素が絡み合う「知覚の対象」であり、客観的な事実である「情報」とは異なります。
情報は論理の対象であり、非人間的だからこそ客観性を保てます。しかし、情報伝達を円滑にするためには、送り手と受け手の間のコミュニケーションが不可欠なのです。
スキル③管理手段の活用
ドラッカー教授は、数字や測定値といった管理手段には、理解しておくべき「3つの特性」があると指摘します。
特性(1):測定すること自体が「主観的な行為」である
観測すること自体が、観測者による価値・意味・関心にもとづいた主観的行為である……20世紀の認識哲学の世界では、このような議論が活発に行われました。
数字を管理するからといって、客観的な立場になれるわけではありません。
「何を測定しようか」という意思決定は、測定者が対象を重要とみなした証であり、その人の価値観や世界観が反映されています。
しかし、それで良いのです。
管理において最も重要な問題は、「いかに管理するか」ではなく「何を測定するか」にあるのです。
特性(2):管理手段は「成果」に焦点を合わせる
効率を測るために単に数字を管理するのではなく、組織が外部の世界(社会、顧客)に貢献している何らかの「成果」を表すものを測定しなければなりません。
売上は組織内部の事情を示す指標であり、必ずしも顧客への貢献度を表しているとは限りません。
たとえば顧客満足度を測るために、「ありがとうの数」や「紹介の数」などを測定する視点が重要です。
特性(3):測定できない事象にも目を向ける
測定できるものは、すでに発生した事実、つまり過去のものです。
ドラッカー教授は、数字では測定できない「知覚情報」を大切にするよう説きます。
外に出て、見て、聞いて、感じた世界の変化を言語化することも、重要なマネジメントスキルなのです。
スキル④経営科学
マネジメントを行う者は、必ずしも経営学者である必要はありません。
また経営学を学んだからといって、事業で成功できる保証もありません。
しかし、経営科学に何を期待でき、どのように活用できるかを知っておく必要があります。
ドラッカー教授は、経営科学を生産的に活用するために、以下の4つの点を期待し、要求すべきだと述べています。
- 【仮説を検証する】経営科学の理論やモデルは、特定の仮定に基づいています。その仮定が現実の状況に合致しているかを常に検証する姿勢が重要です。
- 【正しい問題を明らかにする】経営科学の手法は、問題を分析し解決するのに役立ちますが、そもそも「正しい問題」を設定することが不可欠です。
- 【答えではなく代替案を示す】経営科学は、唯一の正解を提供するものではなく、意思決定のための複数の代替案とその可能性を示すものです。
- 【問題の本質を探るために活用する】経営科学のツールやフレームワークを形式的に適用するのではなく、問題の本質的な理解を深めるために活用することが重要です。
これらの能力を磨き、変化の激しい現代において、組織を成功へと導く卓越したマネジャーを目指しましょう。
マネジャーの条件
ドラッカー教授は、マネジメントに携わる者は現実家であって、評論家であってはならないと警告します。
マネジャーの条件とは一体何なのか?
「マネジャーのスキルがあるかどうかだ」と考える人もいるでしょう。
しかし、マネジメントのスキルは、誰でも身につけることができます。そして、誰でも身につけられるものであるべきだとドラッカー教授はいいます。
マネジメントとは実践である。その本質は知ることではなく、行うことにある。
『マネジメント』より
マネジメント能力は誰かに教えてもらうことはできません。しかし、実践を通じて学ぶことは出来ます。それがマネジメントを身につける、ということです。
掛け算の九九を習ったときのように練習による修得が必要になる。
『経営者の条件』より
トレーニングの結果、無意識に心身が動く状態を「習慣化された」といいます。習慣は第二の才能とも言われます。悪しき習慣をあらため、良き習慣を身につけることが成果への近道です。
ですからマネジメントスキルは習得すれば誰でも身につけることができます。スキルの有無をもって、マネジャーの資格を判断することは、あまり意味がないといえます。
では、マネジャーとして「不適格」なのは、どういった人物なのでしょうか。
これについてドラッカー教授は、「真摯さ」を持つ者であるかを重要な判断材料といいました。
真摯さを定義することは難しい。しかし真摯さの欠如は、マネジメントの地位にあることを不適とするほどに重大である。人の強みよりも弱みに目がいく者をマネジメントの地位につけてはならない。人のできることに目の向かない者は組織の精神を損なう。マネジメントに携わる者は現実家でなければならない。評論家であってはならない。
何が正しいかよりも、誰が正しいかに関心をもつ者をマネジメントの地位につけてはならない。誰が正しいかを気にすると、部下は無難な道をとる。おかした間違いを正すよりも隠そうとする。
真摯さよりも頭のよさを重視する者をマネジメントの地位につけてはならない。有能な部下に脅威を感じる者もマネジメントの地位につけてはならない。そして、自らの仕事に高い基準を設定しない者をマネジメントの地位につけてはならない。
『ドラッカー365の金言』より
真摯さをもつマネジャーを、より具体的にいうと、次のようにも表現することができるでしょう。
親であり教師であれと、ドラッカーは説く。「その者の下で息子を働かせたいか」と問う。部下の人生に関わる存在であれということだ。真摯さのない者をマネジャーにすれば、部下の成長を阻害し、やがて人と組織を破壊する。
『ドラッカー教授 組織づくりの原理原則』(著:佐藤等/編:清水祥行)
まとめ
本稿では、ドラッカー教授の視点から、マネジャーの定義、果たすべき二つの重要な役割、そして日々の仕事における五つのポイントを解説しました。マネジャーは単なる命令者ではなく、チームの力を最大限に引き出し、組織全体の成果に貢献する「責任者」です。短期的な成果と長期的な視点のバランスを取りながら、目標設定、組織化、動機付けとコミュニケーション、評価測定、人材開発という五つの仕事を遂行することが求められます。
さらに、成果を上げるチームづくりには、意思決定、コミュニケーション、管理手段の活用、経営科学への理解という四つの不可欠なスキルが存在します。ドラッカー教授の深い洞察は、これらのスキルを磨き、変化の激しい現代において、組織を成功へと導くための羅針盤となるでしょう。
マネジメントは知識だけでなく、実践であり、日々の積み重ねによって習慣化されるものです。本稿で紹介したドラッカー教授の教えを参考に、あなた自身のマネジメント能力を磨き、チームを率いて大きな成果を上げられる有能なマネジャーへと成長していくことを心から応援しています。

 お気に入りに追加
お気に入りに追加Dラボ
当サイトDラボを運営しております。
ドラッカーを学んだ経営者やビジネスマンが実際に仕事や経営に活かして数々のピンチを乗り越え、成功を収めた実例を記事形式で紹介しています。
また、「実践するマネジメント読書会」という、マネジメントを実践的に学び、そして実際の仕事で活かすことを目的とした読書会も行っております。
2003年3月から始まって、これまでに全国で20箇所、計1000回以上開催しており、多くの方にビジネスの場での成果を実感していただいています。
マネジメントを真剣に学んでみたいという方は、ぜひ一度無料体験にご参加ください。
最新記事 by Dラボ (全て見る)
- 【ドラッカーに学ぶ】マネジャーの役割と仕事は?必要なスキル4選を解説。 - 2025年3月26日
- 【ドラッカー流!チーム作りの極意】成果を出す組織が実践するマネジメントの基本。 - 2025年3月20日
- 企業の強みとは何なのか?競合にはない強みの見つけ方とは。 - 2025年3月5日
- なぜ自分の部下は成長しない?上司として伝えたい成長の秘訣7つを徹底解説。 - 2025年2月19日
- 正しい部下の育て方はある?自己成長を促すために必要な7つのポイントを徹底解説。 - 2025年2月5日
 Facebook
Facebook