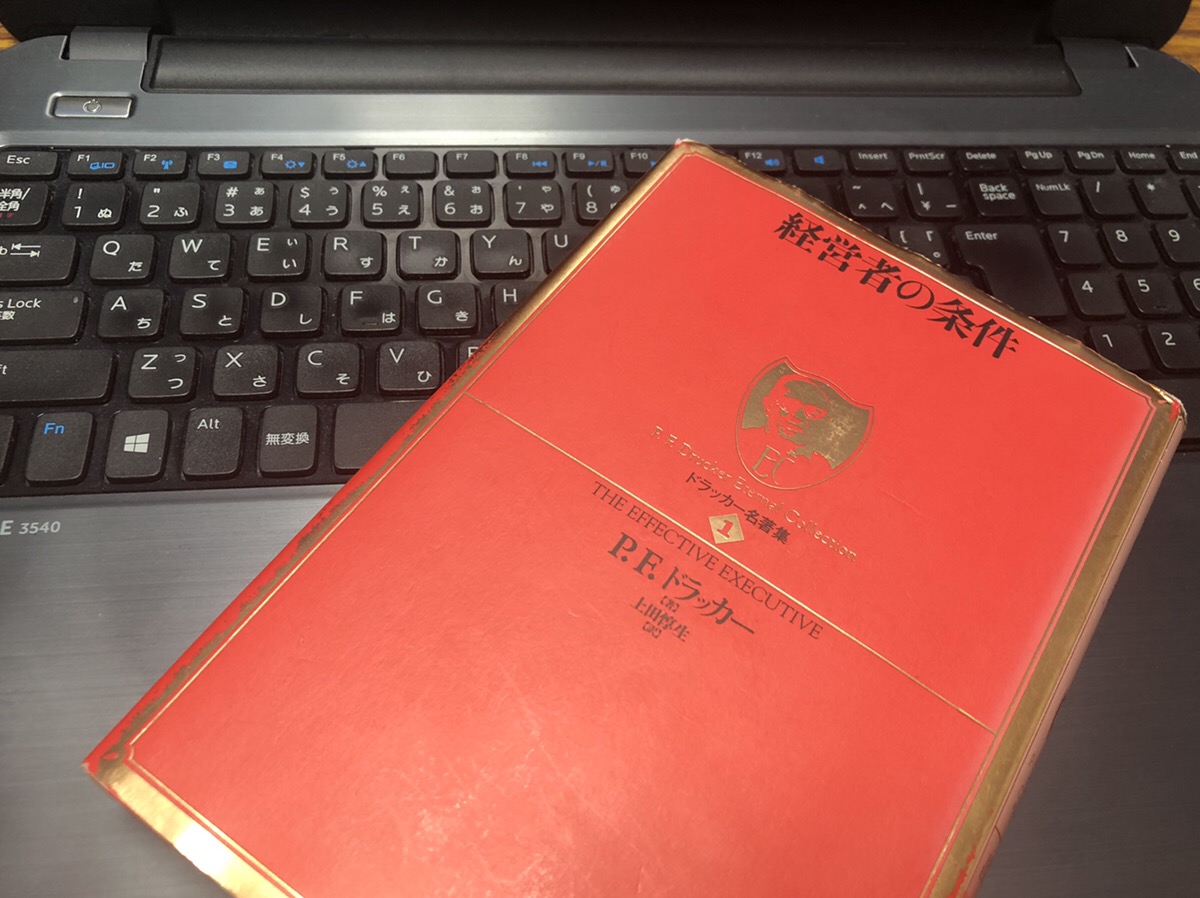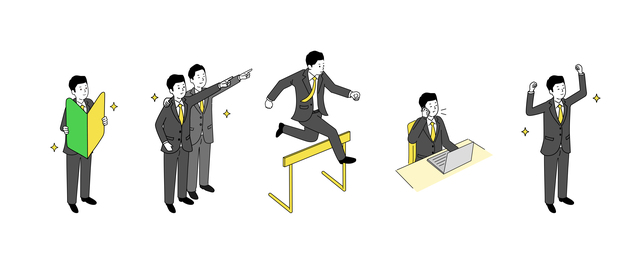
「部下の育て方」は、世界中の上司が直面する共通テーマです。
おそらく、部下を育てることができなかったという経験を持つ方が、大半だと思います。
「具体的な成果を提示できなかった」
「やる気があるので自主的に学んで成長すると思ってた」
「自走できるタイプだから放置していた」
「心配だから仕事のやり方の細部にまで口を出した」
このような苦い経験、あなたもお持ちでしょう。
しかし実は、「部下の育て方」というテーマには、思わぬ落とし穴がひそんでいます。
「部下を成長させるにはどうしたらいいの?」と悩んでいる方に、ぜひ読んでほしい内容となっています。
この記事では、「マネジメント」という概念を開発したピーター・F・ドラッカー教授の金言を借りながら、部下が指導を受けなくてもイキイキと自己成長するために必要な、上司の態度・考え方について、徹底的に解説します。
この記事を読めば、そもそも「人を成長させようとする」という発想自体が、すべての間違いのはじまりだったことに気が付くはずです。
「部下を育てる正しい方法があるはずだ」と考えている方にも、ぜひ読んでほしい内容です。
目次
なぜ部下を育てるのがうまくいかないのか?
まずは以下に、部下育成でうまくいかない理由とともに、部下がイキイキと自己成長するように、上司がどのような考え方をもてばよいのかについてお伝えします。
①「成長させる」という発想が「過干渉」につながる
部下育成というテーマにおいて、最も大切な観点をお伝えします。
それは、「人を成長させる」という発想が、じつは、部下の自己成長の機会を奪ってしまうということです。
「部下を育てるにはどうしたらいいのだろう」と悩んでいる人の多くは、意識的・無意識的に「人を成長させる方法を会得すれば、部下の育成が成功する」と考えているはずです。
しかし、それが落とし穴です。
「成長させる」という発想は、部下への過干渉を当然のことと捉えてしまう危険性があります。
では、人が成長するとは、一体どういうことなのでしょうか。
部下育成は、マネジメントの重要な領域です。
なので、ここでひとつ、マネジメントの概念を開発したピーター・ドラッカー教授の言葉を引用してみましょう。
成長は、常に自己啓発によって行われる。企業が人の成長を請け負うなどということは法螺(ほら)にすぎない。成長は一人ひとりの人間のものであり、その能力と努力に関わるものである
『マネジメント』より
成長に最大の責任を持つ者は、本人であって組織ではない。
『非営利組織の経営』より
なぜ、ドラッカー教授は、成長はあくまでも自分の責任であると言ったのでしょうか。
その背後には、深い意味があります。
- 「人を成長させる」という発想を肯定すると、他者への「干渉」を肯定することになり、
- 「干渉」の肯定は、他者の価値観に踏み込むことを肯定することにつながり、
- 結果として、「成長のためには人をコントロールしてもよい」という命題を是としてしまうからです。
人がイキイキと働き、その過程でみずから成長を欲し、自己充足する。そのプロセスにこそ、真の成長がある。ドラッカー教授は、そう考えていたのです。
②「育てる」のではなく「成長の機会を生み出す」
では、上司として、部下育成というテーマと、どう向き合えばよいのでしょうか。
「成長させる」という発想が誤っているのだとしたら、自分は部下に何ができるのだろう……?
当然の疑問です。
ポイントは「自己決定」と「有能感」だ。社員に自ら考え、行動させる。そこから自ら成長したいという意欲が芽生え、自身の成長度合いを測る、自分なりの物差しができる。自己決定し、自己評価できることが有能感の源泉だ。
佐藤等『ドラッカー教授 組織づくりの原理原則』より
今後、ぜひ意識してほしいのは、部下がみずから成長するように、機会と環境を生み出すことです。
人は人を「成長させる」ことはできませんが、自己開発を行うように「方向付ける」ことはできるのです。
自己開発とは、人から教えられることの限界を理解し、みずから学ぶ姿勢を身につけ、行動することです。
成果をあげる道は、尊敬すべき上司、成功している上司をまねることではない。(中略)指紋のように自らに固有の強みを発揮しなければ成果をあげることはできない。
『非営利組織の経営』より
結局、わたしたちは、一人ひとりが自分と向き合い、知識やスキルを磨き、成果をあげるしかないのです。それは上司であるあなたも、伸び悩んでいる部下も、みな同じです。
③「正しい部下の育て方がある」という発想を捨てる
“ノウハウコレクター”という言葉を聞いたことはありますか?
ノウハウコレクターとは、たとえばビジネス書を熱心に読み漁る人のことを指します。
彼らは、さまざまな“情報”を知ってはいるし、“批評”はするけれども、実践をしないので、何の変化も起こしていません。
そんな彼らのよくある口癖が「いろんな本を読んできたけど、だいたい言っていることは同じ」です。
なるほど、仮に言っていることが同じであるなら、すぐに実践すれば効果がでるはずなのに、なかなか行動にうつさない……それはなぜでしょうか?
もしかしたらノウハウコレクターは、自分の納得のいく「絶対に間違いのない攻略法」なるものを探し求めて、本を読んでいるのかもしれません。
ドラッカー教授はそのような考え方を「追い求めてはいけない賢者の石」と揶揄しました。
人材育成にあたっては、当然、ノウハウコレクターではいけません。
巷にあふれる「人材育成の方法論」に関する書物は、うわべだけの情報、まさに“ノウハウ”でしかありません。
必要なのは、マネジメントにおける「原理」と「方法」の区別です。
「原理」というのは、人間存在に関わることです。
人間とは何か?人間とはどのような動物なのか?人間はどのようなときにどのような感情を抱くのか?……
人間は感情をもっています。多様な価値観・世界観で生きています。マネジメントを行うには、そんな複雑な存在である人間が対象であるという自覚が必要です。
すなわちマネジメントにおける「原理」とは、「これさえやればうまくいく」という“正解”を教えるものではありませんが、「ここから逸脱すれば破綻する」という“戒め”を理解するためものなのです。
基本と原則に反するものは、例外なく時を経ず破綻する。
『マネジメント―エッセンシャル版』より
一方で「方法」とは、特定の目的や特定の状況に合わせて“使い分ける道具”です。
「ものが燃焼する」という原理を理解していれば、火の大きさに応じて、方法を使い分けて消化することができます。
アルコールランプの火を消すならば、フタをかぶせるだけでよいでしょう。焚火を消すならば、バケツの水をかければよいですね。では、山火事を鎮火するには?
このように、原理さえ理解していれば、状況にふさわしい方法を適用することで、適切な成果を得ることができます。
ところが、原理と方法を混同すると、大変です。こと「人」にまつわるマネジメントにおいては、人を傷つけ、害をなすことになります。
すでに半世紀以上前から、人間の働く動機が「金銭」では充足しえないことを指摘するドラッカー教授は、次のように言います。
……人のマネジメントの仕方は、まったく同じではありえないことを意味する。同じ種類の人たちでさえ、状況の変化によって、マネジメントの仕方が変わってこなければならない。(中略)したがって、とくにこれからは、人をマネジメントすることは、仕事をマーケティングすることを意味するようになる。マーケティングの出発点は、組織が何を望むかではない。相手が何を望むか、相手にとっての価値は何か、目的は何か、成果は何かである。
『明日を支配するもの』より
部下が育てるために上司ができること
以下では、部下がみずから成長する「機会」「環境」を生み出すために、具体的に実践できるポイントを紹介します。
マネジメントの概念の開発者であるドラッカー教授の言葉も引用します。気づきやヒントが得られるはずです。
究極のポイントは、ともに働く人を理解するということです。
上司と部下の相互理解こそ、部下の成長を大きく促すきっかけとなるのです。
……人もまた自分と同じように、人であるという事実を受け入れることである。誰もが人として行動する。すなわち、それぞれの人がそれぞれの強みをもつということである。それぞれの仕方をもち、それぞれの価値観をもつということである。
『非営利組織の経営』より
①不得意なことで仕事をさせない
ドラッカー教授は、「人を育てる」ことについて、“ばかばかしい間違い”が4つあると言っています。その一つが、不得意なことで何かを行わせる、です。
学校では教師に「タカシ君は作文はうまいが、分数が弱いので、もっとやらせてください」と指摘されます。ようするに“弱み”にフォーカスされるのです。
社会で生きるために必要最低限の知識を習得させるという点では、分数という弱みを指摘するのは、間違ってはいないかもしれません。
ところが、社会に出て、組織で働くようになると、「強み」をもった人材が、はるかに重要となります。
ドラッカー教授は「不得意なことで何かを行わせてはならない」と戒めます。
成人して働くようになった頃には、個性はできあがっている。礼儀、態度、スキル、知識は学ぶことはできる。だが個性を変えることはできない。
『非営利組織の経営』より
われわれは気質と個性を軽んじがちである。だがそれらのものは、訓練によって容易に変えられるものでないだけに、重視し、明確に理解することが必要である。
『非営利組織の経営』より
ここで「個性」という言葉に注目してください。
あなたは部下に、不得意なやり方で仕事をさせていませんか?
人にはそれぞれ、得意とするやり方があります。
情報を集めるのに「聞く」ほうが得意な人もいれば、「読む」ほうが得意な人もいます。
情報を伝えるのに「話す」が得意な人もいれば、「書く」ほうが得意な人もいます。
あなたが「聞く」のが得意だからといって、部下がそうである根拠はありません。
いまいちど、部下の得意な仕事のやり方について、本人とじっくり向き合ってみてはいかがでしょうか。
②仕事と人生の目標と結びつける
ドラッカー教授は、「近視眼的に人を育ててはならない」と言います。
身につけさせるべきスキルはある。だが人を育てるということはそれ以上のことである。キャリアと人生に関わることである。仕事は人生の目標に合わせなければならない。
『非営利組織の経営』より
ドラッカー教授は、13歳のとき、宗教の先生に「何によって憶えられたいか」と訊かれました。「答えられると思って聞いたわけではない。でも50歳になって答えられなければ、人生を無駄に過ごしたことになるよ」と先生は言いました。
以来ドラッカー教授は、生涯にわたって、自己刷新を行うための問いとして「何によって憶えられたいか」を自分に投げかけていたそうです。
あるときドラッカー教授は、かかりつけの歯科医に同様の質問を行いました。
すると歯科医は「あなたを死体解剖する医者が、(歯を見て)この人は一流の歯科医にかかっていた」と言ってくれることだ――と答えたそうです。
「何によって憶えられたいか」という問いは、仕事を通じて、人生そのものにまたがる究極の問いです。ここにおいて仕事観と人生観が一致しています。
抽象的で、壮大のようにも思えるかもしれません。
しかし「何によって憶えられたいか」という問いを、部下と共に考えるだけで、本人のモチベーションにつながるのではないでしょうか。
③エリート扱いしない
転職した人が、思うように成果をあげられず、挫折することがよくあります。
前職で成果をあげていた人ほど、その落とし穴にはまる可能性があるのです。
有名大学出身の新卒者もまた同様に、頭はいいのに、なかなか成果をあげられない人がいます。
なぜでしょうか?
それは、過去の業績や、成功をもたらしたやり方に固執するあまり、いまの組織が自分に求めていることは何かを考えていないからです。
最もよく見られる人事の失敗は、新たに任命された者が新しい地位の要求に応えて自ら変化していくことができないことに起因している。それまで成功してきたことと同じ貢献を続けていたのでは失敗する運命にある。
『経営者の条件』より
まずは、組織として、上司として、部下に期待することを明確に伝えてみましょう。
そこではじめて、部下は組織における「位置と役割」を理解し、期待される成果のために、意味のある努力を行えるようになります。
④部下の強みに目を向ける
マネジメントのなかでも、とくに「人の強みを生かす」は、きわめて重要な領域です。
「組織の役割は、一人ひとりの強みを共同の事業のための建築用ブロックとして使うところにある」とドラッカー教授は言いました(『経営者の条件』)。
部下の弱みに焦点を合わせることは、間違っているばかりか無責任である。上司たる者は、組織に対して部下一人ひとりの強みを可能なかぎり生かす責任がある。
『経営者の条件』より
学校教育では、できることよりも、できないことに目を向けがちです。
国語の成績が5で他が評定3の生徒よりも、評定オール5の生徒のほうが優秀であると錯覚します。
学校において「成績」というのは、あくまでも個人のなかで完結します。
しかし組織においては、強みだけが重要です。強みこそ、組織が成果をあげ、社会貢献するためのカギとなるのです。
大きな強みをもつ者はほとんど常に大きな弱みをもつ。山あるところには谷がある。しかもあらゆる分野で強みをもつ人はいない。人の知識、経験、能力の全領域からすれば、偉大な天才も落第生である。申し分のない人などありえない。そもそも何について申し分がないかも問題である。
『経営者の条件』より
⑤ミッションを感じさせる
部下が視座を高くし、仕事と自己成長とが連動するようになるには、まずは組織のミッション(使命)を理解するところから始めよと、ドラッカー教授は言います。
なぜなら、ミッションの理解こそ、「貢献」の意欲を刺激するからです。
組織に働く者の場合、自らの成長は組織のミッションと関わりがある。(中略)仕事のできないことを、設備、投資、資金、人手、時間のせいにしてはならない。それではすべてを世の中のせいにしてしまう。よい仕事ができないのをそれらのせいにすれば、あとは堕落への急坂である。
『非営利組織の経営』より
ですから上司は、一人のリーダーとして、組織のミッション(使命)を部下にしっかり伝えることが大切です。
……自己開発は、その成果の大部分が貢献に焦点を合わせるかどうかにかかっている。組織に対する自らの貢献を問うことは、いかなる自己開発が必要か、いかなる知識や技能を身につけるか、いかなる強みを仕事に適用するか、いかなる基準をもって自らの基準とするかを考えることである。
『経営者の条件』より
⑥セルフマネジメントの大切さを伝える
「誰かに教えてもらえば、(自然に)成長できる」という誤解は、いつから身についてしまったのでしょうか。
講座方式で一方的に授業を行う学校教育の世界が、わたしたちの「学び」「成長」のステレオタイプとしてこびりついてしまっているのかもしれません。
これまで説明したとおり、「学び」「成長」の本質は、つまるところ自己開発です。自分が自分自身をマネジメントすることが求められるのです。
ですからあなたは上司として、自己開発の重要性を伝える責任があります。
世の中には「成長できない人はこんな人」という解説を散見しますが、マネジメントの観点からいえば、成長できない人はいません。
私は、成果をあげる人のタイプなどというものは存在しないことにかなり前に気づいた。私が知っている成果をあげる人は、気質と能力、行動と方法、性格と知識と関心などあらゆることにおいて千差万別だった。共通点はなすべきことなす能力だけだった。
『経営者の条件』より
ではなぜ、部下が成長できずにくすぶっているかというと、成果をあげる習慣が身についていないだけなのです。
成果をあげる人に共通するものは、つまるところ成果をあげる能力だけである。企業や政府機関で働いていようとも、病院の事務長や大学の学部長であろうとまったく同じである。いかに聡明、勤勉、創造的、博識であろうと、成果をあげる能力に欠けるならば成果をあげることはできない。
『経営者の条件』より
では具体的にどのような習慣を身につければ、成果をあげる人材へと成長を遂げることができるのでしょうか。
簡単に要約しますと、次の5つに要約できます。
- 時間を管理する
- 外の世界への貢献を意識する
- 自分・上司・同僚・部下の強みを生かせ
- 物事の優先順位を決めて集中せよ
- 成果のあがる意思決定を行う
詳細については、以下の記事をご覧ください。そしてもし興味がでたら、セルフマネジメントの世界的名著『経営者の条件』の本書を手に取ってみてください。
⑦先生役をしてもらう
「人に教える」ということが、どれだけ自己成長にとって意義があるのかは、すでにあなたも身をもって経験していることでしょう。
人の育成にあたって最も効果的な方法が、先生役をしてもらうことである。先生になることほど多くを学べることはない。先生役を頼むことは最高の評価である。営業マンであれ赤十字のボランティアであれ、「どうして成績がよいのか、話してください」と頼まれるほど、うれしいことはない。
『非営利組織の経営』より
花形セールスマンの生産性をさらに向上させる最善の道は、セールスマン大会で成功の秘訣を語らせることである。外科医の成果を向上させる最善の道は、地域の医者の集まりで自らの仕事について語らせることである。看護師の成果を向上させる最善の道は、新人の看護師に教えさせることである。
『プロフェッショナルの条件』より
部下に「人に教える機会」を提供することは、まさに成長のための環境づくりの一手です。やり方はいくらでも思いつきそうですね。ぜひトライしてみてください。
さいごに:相互理解こそ、部下育成のカギ!
以上、「部下育成」をテーマに、部下育成がうまくいかない理由・部下育成のポイントを紹介しました。
今回の内容をぎゅっと濃縮して一言であらわすと、「上司と部下の相互理解」です。
一般的には、「上司が部下を育てる」という一方通行な考え方が当然視されています。「成長させるメソッド」なるものが世の中にあふれているのも、うなずけます。
しかしこの記事では、マネジメントの開発者であるドラッカー教授の金言を借りながら、
部下を育てる方法があるのではなく、上司と部下が相互理解を通じて、成長する機会を共に生み出していくことの重要性を伝えました。
組織は、もはや権力によっては成立しない。信頼によって成立する。信頼とは好き嫌いではない。信じ合うことである。そのためには、互いに理解していなければならない。互いの関係についてお互いに責任をもたなければならない。それは義務である。
『明日を支配するもの』より
この記事を読んで少しでもタメになったと思ったら、ぜひ他の記事も読んでみてください。

 お気に入りに追加
お気に入りに追加Dラボ
当サイトDラボを運営しております。
ドラッカーを学んだ経営者やビジネスマンが実際に仕事や経営に活かして数々のピンチを乗り越え、成功を収めた実例を記事形式で紹介しています。
また、「実践するマネジメント読書会」という、マネジメントを実践的に学び、そして実際の仕事で活かすことを目的とした読書会も行っております。
2003年3月から始まって、これまでに全国で20箇所、計1000回以上開催しており、多くの方にビジネスの場での成果を実感していただいています。
マネジメントを真剣に学んでみたいという方は、ぜひ一度無料体験にご参加ください。
最新記事 by Dラボ (全て見る)
- 【ドラッカーに学ぶ】マネジャーの役割と仕事は?必要なスキル4選を解説。 - 2025年3月26日
- 【ドラッカー流!チーム作りの極意】成果を出す組織が実践するマネジメントの基本。 - 2025年3月20日
- 企業の強みとは何なのか?競合にはない強みの見つけ方とは。 - 2025年3月5日
- なぜ自分の部下は成長しない?上司として伝えたい成長の秘訣7つを徹底解説。 - 2025年2月19日
- 正しい部下の育て方はある?自己成長を促すために必要な7つのポイントを徹底解説。 - 2025年2月5日
 Facebook
Facebook