<「ドラッカーの本でも読んでおけ」という言葉に応えるためのドラッカー本を読む順番>と題して全7回で説明をしてきました。今回の連載は、読む順番を「目的別」に示したものです。
私たちの読書会―「実践するマネジメント読書会®」では、目的別読むためのプログラムを開発してきました。その経験からどのドラッカー本のどの章を、どんな順番で読めばいいのかを長年考えてきました。この連載ではこの一端を紹介してきました。
『もしドラ』は読んだけど…
目的別に読む理由は、読者の動機にあります。「ドラッカーの本でも読んでおけ」との言葉に代表されるようにドラッカー教授の著作を手にされる多くの方は、組織でマネジメントを必要としている人や将来必要になるだろう人ではないでしょうか。
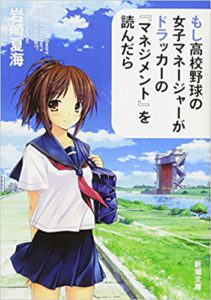
私たちの読書会にもそのような方々が多数足を運んでいます。しかし、実際には『もしドラ』をよんでエッセンシャル版『マネジメント』を読もうとしたけれども挫折したという方が非常に多いのです。これは一つの典型的な例ですが、要はどこからドラッカー教授のマネジメントを学んだら良いかわからない方が多いのです。
たとえばエッセンシャル版『マネジメント』は、第1章は事業のマネジメントから始まります。個別の商品やサービスしか扱ったことがない経営者や事業を統括する担当者以外の人が読んでもイメージが湧きにくいはずです。未経験の領域について想像力を働かせて読み進めることは苦痛以外の何ものでもなく、そればかりか誤解しながら読むリスクを常に抱えています。
どうしてもエッセンシャル版『マネジメント』から読み始めたい思う方は、第3章の人と仕事のマネジメントから読み始めるとよいでしょう。
死してなお生成発展するマネジメント
このようにドラッカー教授の本は、それぞれの立場や状況などに応じて読むべき本と章が異なります。『マネジメント』がカバーするマネジメントの領域は広く、百科事典のような位置づけです。百科事典の1ページから読むのは大変な苦労が伴います。
ドラッカー教授の著作群は、何十年も前の問題意識を前提に長い年月をかけて結論に至っています。したがってその断片を読んでも理解しにくい傾向があります。目的別に読むことは、これらの時間的な変遷も意識しながら読むことになります。そうして初めてそれぞれのテーマの意味を知ることになります。
この過程は、遠回りのようですが、真のマネジメント力を修得する基礎となります。ドラッカー教授のマネジメントは新しい現実を前に、新たな課題が生まれれば、それを解決するために普遍性の高い原理を用いて新たな方法を導き出す力を有しているからです。
ドラッカー教授は死してなおマネジメントが生成発展するように知識を体系立てたのです。ここまで修得してはじめてマネジメント力が身についたといえましょう。
ドラッカー山脈を踏破する登山プラン
その意味でドラッカー教授のマネジメントを学ぶための入り口は多様です。大きく分けても事業のマネジメント、仕事のマネジメント、人のマネジメント、セルフマネジメントがあります。どこから学ぶことも可能ですが、おすすめはセルフマネジメントです。
幸せな人生を送るために万人に必要な知識だからです。組織は器にすぎません。その中にある本質的な経営資源は、知識とそれを生み出し、保有し、運用する人です。ドラッカー教授は彼らを知識労働者と呼びました。それゆえ知識労働者のセルフマネジメントこそがマネジメントの根幹です。
人材育成とは、他人の自己開発を支援することです。そして自己開発は、業務的な知識やスキルを身につけるとともに成果をあげる能力を修得することです。成果をあげる能力こそはセルフマネジメント中核にあるものです。それゆえマネジメントの入り口を知識労働者のセルフマネジメントをおすすめしています。
マネジメントを実践で身につけたい方は、①セルフマネジメント、②仕事のマネジメント、③人のマネジメント、④事業のマネジメントの順でおすすめしています(本連載の第1回目、第2回目、第3回目と第4回目という順番です)。
とりわけ人の意識改革を含めた組織改革などを進める際には、この順番が一番です。もちろん④の一部を早目に取り組むなど実際には状況に合わせて微調整が必要です。
さて目的別に読む理由は、結局、実践でマネジメントを導入する際に最適な順番という一つの結論に達します。40冊近くあるドラッカー教授の著作はときにドラッカー山脈といわれます。しかしその入り口を間違うと山頂に到達できません。マネジメントという偉大な遺産が過去のものにならないためにも適切な登山プランの下に挑戦することをおすすめしています。
善き世の中を実現するためにも多くの方に挑戦して欲しいものです。
「ドラッカーの本でも読んでおけ」という言葉に応えるための本を読む順番(連載記事)
第1回:すべての社会人の方に…
第3回:新規事業の立ち上げなど事業のマネジメントに悩むマネジャーや経営者の方に…
第5回:ドラッカーマネジメントの「一丁目一番地」を知り、真のマネジメントを行いたい方に…
第6回:未来の社会はどのように変化するのか?予見力を高めたい方に…
第7回:<付録>目的別に読む理由はどこにある
※本格的にドラッカー教授の著作に取り組みたい方には、発行年代順に読まれることをおすすめしています。この読み方の最大の目的は、ドラッカー教授の思考の形成プロセスを感じながら読むことにあります。
(連載終わり)

 お気に入りに追加
お気に入りに追加最新記事 by 佐藤 等 (全て見る)
- ドラッカーマネジメント流③【アフターコロナを意識した事業と仕事のマネジメント】「#わたしの非常事態宣言—でも悪いことばかりではないぞ」(佐藤等) - 2020年5月6日
- ドラッカーマネジメント流②【アフターコロナを意識した事業と仕事のマネジメント】「#わたしの非常事態宣言—でも悪いことばかりではないぞ」(佐藤等) - 2020年4月19日
- ドラッカーマネジメント流①【アフターコロナを意識した事業と仕事のマネジメント】「#わたしの非常事態宣言—でも悪いことばかりではないぞ」(佐藤等) - 2020年4月10日
- 100万部発行のエッセンシャル版『マネジメント』を『実践するドラッカー』の著者佐藤等(ドラッカー学会理事)が名言とともに実践ポイントを要約解説する - 2020年4月7日
- 「美しい会社とはなにか?」著者佐藤等が語る『ドラッカー教授 組織づくりの原理原則』の読み方使い方―マネジメントとリーダーシップの関係もわかりやすく解説 - 2019年12月23日
 Facebook
Facebook






