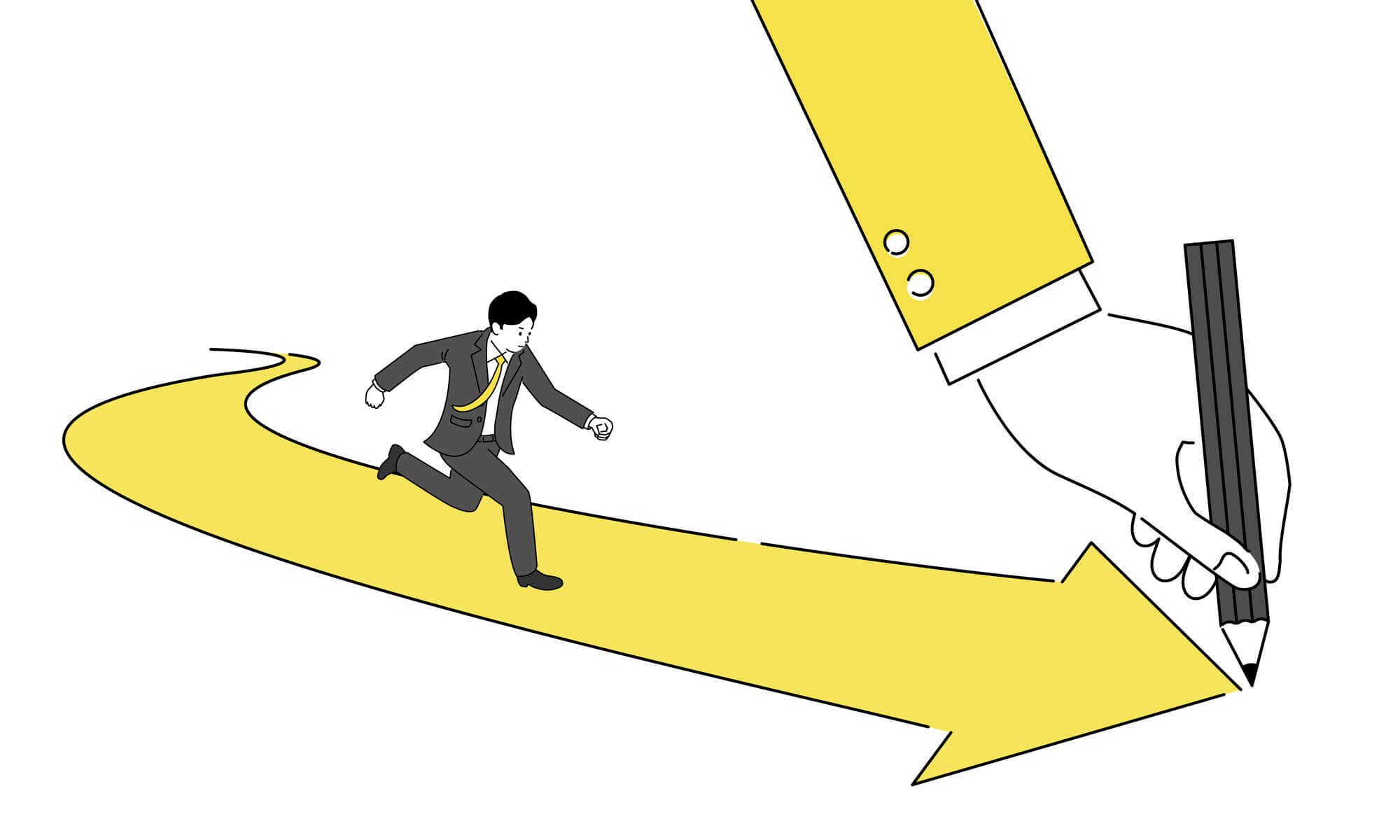信頼していた部下に退職を告げられた時のショックは計り知れないでしょう。
この記事では、部下が退職してしまう原因やその前兆、また退職したいと部下に言われた時の対処法を、まずは一般論の視点で概説するとともに、次に“マネジメントの父”ことピーター・F・ドラッカーの視点で何が言えるかを論じます。
ドラッカーの視点には、上司として部下にどう接するべきか、という原理原則が凝集されています。
一般的には「部下としっかり向き合い、ちゃんと悩みを聞いてあげなさい」という結論に達しがちですが、そう簡単ではありません。
なぜなら、「ちゃんと悩みを聞くよ」と言って相手が素直に応じてくれるほど、心境は単純ではないからです。
たいていの場合、「悩みを聞くよ」と部下に言わざるをえない時点で、部下の心はすでに決まっていると思います。
ドラッカーの視点を学べば、部下がモチベーションを失ってしまう前の段階でアプローチする必要性を理解できることでしょう。
ポイントは、あなたが「信頼している部下」だと思っている相手と、本当の意味で信頼関係を築けているのかという点です。
目次
【結論】信頼していた部下の退職を防ぐ対策は「マネジメント」を見直すこと
あらゆるマネジメント上の間違いは、人としてのマネジメントによるものである。人としてのマネジメントのビジョン、献身、真摯さが、マネジメントの成否を決める
ドラッカー『マネジメント』
組織で起こるさまざまな問題の多くは、マネジメントの問題に行き当たります。問題を放置していれば、同じ悲劇が繰り返されるだけです。以下に、信頼していた部下の退職を未然に防ぐための9つの対策方法をまとめました。
①マネジメントは「一人の人間と向き合う」ことから始まる
マネジメントの語源はイタリア語の「馬を馴らす」(maneggiare)に由来し、「手綱を操る」というニュアンスを含んでいます。
馬には性格、意志、気分、得意・不得意があり、これは人間と同じです。
目指すべきゴールは一つでも、その道程はそれぞれ異なります。
そして、ゴールに向かう過程で何に苦痛や喜びを感じ、人生の意義を見出すかも人それぞれです。
こうした個性豊かな馬をゴールへ導くためには、目の前の馬と真摯に向き合い、その個性を認めた上で、その馬に合った方法で強みを活かしながら目標へと導かなければなりません。
このように、「馬を馴らす」という比喩的な意味が転じて、managementは「物事をうまく扱うこと」、すなわち組織やプロジェクトに関わる人々を統率し、目的達成へと導くことを意味するようになりました。
つまるところ、マネジメントの核心は「人」です。意志も感情もない車をハンドリングし、ゴールへと導くのとはわけが違います。意志も感情も願望もある「人」を、いかに正しく方向づけ、成果をあげるか……。
ドラッカーは次のように言います。
マネジメントとは、仕事の絆で結ばれたコミュニティの組織において機能すべきものである。共有する目的のもとに、仕事の絆で結ばれたコミュニティとしての組織のものであるからこそ、マネジメントとは人にかかわることであり、善悪にかかわることである。
ドラッカー『365の金言』より
②「相手の話を聞く」ということは「意見の不一致を肯定する」ということ
成果をあげる者は、意図的に意見の不一致をつくりあげる。そうすることによって、もっともらしいが間違っている意見や、不完全な意見によってだまされることを防ぐ。(中略)一つの行動だけが正しく、他の行動はすべて間違っているという仮定からスタートしてはならない。「自分は正しく、彼は間違っている」という仮定からスタートしてはならない。そして、意見の不一致の原因は必ず突き止めるという決意からスタートしなければならない。
ドラッカー『プロフェッショナルの条件』より
あなたの信頼していた部下が、モチベーションを失ってしまうとしたら、「マイクロマネジメント」の可能性を追求すべきかもしれません。
マイクロマネジメントは、相手の一挙手一投足に口を出して細かく指示するやり方ですが、さらに問題なのは、相手の意見を聞き入れないという点です。
マイクロマネジメントは相手のモチベーションと自主性を奪ってしまうNG手法のひとつ。
では、どうすればよいのでしょうか。
まずは、相手に考える余地を十分に与えることが大切です。成果という名のゴールを明確にしたうえで、そこから逆算して、成果をあげるための創意工夫の余地を与えるのです。
ポイントは「自己決定」と「有能感」だ。社員に自ら考え、行動させる。そこから自ら成長したいという意欲が芽生え、自身の成長度合いを測る、自分なりの物差しができる。自己決定し、自己評価できることが有能感の源泉だ。
佐藤等『ドラッカー教授 組織づくりの原理原則』より
③最良のコミュニケーションは「貢献」意識の共有から生まれる
成果をあげるためには、貢献に焦点を合わせなければならない。手元の仕事から顔をあげ、目標に目を向けなければならない。「組織の成果に影響を与える貢献は何か」を自らに問わなければならない。すなわち、自らの責任を中心に据えなければならない。
『プロフェッショナルの条件』
「話に耳を傾ける」だけではコミュニケーションがうまくいくとは限りません。
最良のコミュニケーションを生み出す秘訣は「自分はいかなる貢献を行うべきか」という問いかけです。
上司と部下が互いに「自分はいかなる貢献を行うべきか」という問いを行う過程で、認識の齟齬があることが判明するかもしれません。
しかしその認識に違いがあるという理解こそ、本当によいコミュニケーションが始まります。
④真のリーダーシップとは行動で示すこと
効果的なリーダーシップの基礎とは、組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に定義し、確立することである。リーダーとは、目標を定め、優先順位を決め、それを維持する者である。もちろん、妥協することもある。(中略)リーダーは、妥協を受け入れる前に、何が正しく、望ましいかを考え抜く。リーダーの仕事は、明確な音を出すトランペットになることである
ドラッカー『プロフェッショナルの条件』より
【真のリーダーシップと似非リーダーシップ】
- 真のリーダーは、言動に一貫性がある
- 真のリーダーは、組織の使命に矛盾がないように意思決定をする
- 真のリーダーは、責任は常に自分にあると理解している
- 真のリーダーは、部下を恐れない
- 真のリーダーは、優秀な部下を自らの誇りとする
- 真のリーダーは、自分が去った後に組織が崩壊することを恥とする
- 似非リーダーは、自らのカリスマ性で破滅する
- 似非リーダーは、柔軟性がなく、変化を恐れる
- 似非リーダーは、地位や特権を守るために部下を恐れる
- 似非リーダーは、自分が組織の支配者であると錯覚する
⑤組織の価値観と本人の価値観が一致しているかを気にかける
組織には価値観がある。そこに働く者にも価値観がある。組織において成果をあげるためには、働く者の価値観が組織の価値観になじまなければならない。同一である必要はない。だが、共存できなければならない。さもなければ、心楽しまず、成果もあがらない。
ドラッカー『プロフェッショナルの条件』
自身の強みと組織の価値観が合っているか? 極めて重要な観点です。
たとえ、その仕事で強みを活かせていようとも、価値観に合わないのであれば、人生は灰色になります。「つまるところ、優先すべきは価値観である」とドラッカーは言います。
かつてドラッカーも、ロンドンの投資銀行では強みを発揮して仕事は順風満帆でした。
しかし彼は、世の中に貢献しているという実感が湧かなかったといいます。
そこでドラッカーは、世界恐慌で次の仕事のアテがあるわけでもないにもかかわらず、投資銀行を辞める決意をしました。当時を振り返り、ドラッカーはそれが正しい行動だったと自負しています。
⑥弱みではなく強みに目を向ける
弱みに焦点を合わせることは、間違っているだけでなく、無責任である。上司は、組織に対して、部下一人ひとりの強みを可能なかぎり生かす責任がある。何にもまして、部下に対して、彼らの強みを最大限に生かす責任がある。
ドラッカー『プロフェッショナルの条件』より
成果をあげるためには「人の強み」を生かしましょう。人の強みを生かすことは組織に特有の機能です。
組織とは、強みを成果に結びつけ、弱みを中和し無害化するための道具なのです。
強みと弱みはコインの表と裏。かならず弱みがついてきます。
したがって人事では、“人の弱みを最小限に抑える”という発想ではなく、“人の強みを最大限に発揮させる”という視点で行う必要があります。
なぜなら「人の弱み」に配慮した人事は平凡な結果に終わるからです。
⑦事業のミッションを共有しよう
上司として、「何のために仕事をするのか」としっかりと意義を説明できるようになりましょう。
つまり、事業の使命(ミッション)を理解しなければなりません。カネのために仕事をするだとか、そういった打算的な話ではなく、その仕事がどんな人を幸せにするのかという観点から話をするようにしましょう。
⑧「貢献」意識の共有からスタートしよう
自らの仕事や他との関係において、貢献に焦点を合わせることによってよい人間関係がもてる。そうして人間関係が生産的となる。生産的であることが、よい人間関係に唯一の定義である。
(ドラッカー『経営者の条件』より)
部下と真の信頼関係を持つには、単純に「信頼しているよ」「これからも頼りにしているよ」という言葉だけでは足りません。ドラッカーは、本当の意味で成果をあげる人間関係とは、「貢献」をキーワードにして話し合える関係なのだといいました。
よく「退職を防ぐためにコミュニケーションを増やそう」という解決方法が提示されますが、会話を増やしたり、一緒にご飯に行ったりするだけでは不十分です。ドラッカー的にいうと、本当の中身のあるコミュニケーションとは、「貢献」を主題にした会話です。
- 「組織、および上司である私は、あなたに対しどのような貢献の責任を期待すべきか」
- 「あなたに期待すべきことは何か」
- 「あなたの知識や能力を最も活用できる道は何か」
⑨内発的動機でモチベーションを高めよう
有名な心理学実験でも示唆されているように、人は、お金や人事評価といった外発的動機では、心のモチベーションを得ることができないといわれています。
外発的動機は、モチベーションを削ぐどころか、本来の目的を見失わせ、ときには不正を誘因することもあるのです。人の真のモチベーションは、上述したように「使命」や「貢献」の意識から生まれます。内発的動機を促す組織づくりを目指しましょう。
信頼していた部下が退職する原因まとめ
以下ではよくある原因をまとめて解説します。その中には、部下本人の問題で対処しようがないケースもありますが、上司としての在りかたを見直すことで、次に活かすことも可能です(それについは後述します)。
①上司に不満がある
「おれに不満があるなら遠慮なく話してほしい」と言われて、本当に素直に不満を述べるのは、部下の立場的に難しいものがあります。もともと仲がいいなら尚更言いにくいでしょう。
もし上司に不満があるとすれば、以下の項目がありがちです。
- 口出しが多くて仕事が窮屈に感じる
- 仕事の価値観が合わない
- 上司が正しいと思ったやり方を押し付けられて嫌
- 自分の実力を評価してくれない
②報酬に不満がある
金銭的動機でモチベーションをあげることはできないが、最低限の金銭的な評価は不可欠です。部下の自己評価と会社の評価が一致していなければ、「自分はもっと稼げるはずなのに!」と不満を抱いてしまうかもしれません。
③報酬しかモチベーションがない
逆もまたしかりで、報酬(お金)だけが仕事における唯一のモチベーションになってしまうと、精神的に疲弊してしまうこともあります。「たくさんカネは払っているんだからやる気は十分だろう」と考えるのは危険です。人はそういった外発的動機だけでは真のモチベーションを得ることができません。
④仕事の意義を見失う
上述した話と近いですが、人は仕事の意義を見失うと、著しくモチベーションが下がってしまうものです。理由は様々あると思いますが、「誰かの役に立っているという実感が得られない」「自分の仕事に誇りを持てない」という悩みを持つ部下もいるかもしれません。
部下が退職する前の前兆
信頼していた部下の突然の退職も、部下にとっては、「いきなり」ではないのです。部下の退職の前兆が掴めれば、退職の意思が固まる前にこちらから話しかけることできます。
見た目の変化
髪型や服装などに明らかな変化がある場合は、別業種への転職活動を行っている可能性があります。身だしなみが乱れ始めたときは、部下がこの会社での評価や評判はどうでもいいと感じ始めたサインかもしれません。
業務のモチベーションの低下
以前は積極的だったのに、言われた仕事だけをやるようになったり、集中力が欠けている場合は、モチベーションが低下していると言えるでしょう。トイレ休憩等の離席が増えることはサインの一つです。
コミュニケーションの消極化
前までは明るくあいさつを交わしていたのに、顔色が暗かったり返事が小さかったりしていないでしょうか。また、特別な理由も無いのに、飲み会に参加する回数が減っているかもしれません。周囲との雑談が減り、最低限の仕事の話をするようになったら注意しましょう。
遅刻・欠勤の増加
いつもは余裕をもって出勤していた部下が、始業ギリギリに来るようになり、欠勤が増えた場合は、仕事に気が向かず、悩みや不安を抱えている可能性があります。仕事を休んで転職活動をしているかもしれません。
さいごに:部下の育成・マネジメントで成果をあげるなら「理解」よりも先に「実践」が大切
「わかる」と「できる」は意味がまったく違う――と言われれば、多くの人が「その通りだ」と答えると思います。
しかしマネジメントをわかったつもりになって、なかなか成果をあげられないと悩む人も少なくありません。
Dラボでは、“ドラッカーを実践”するための読書会を開催しています。なぜならドラッカー自身が、「真の理解は実践のあとにくる」と考えていたからです。
ドラッカーの読書会を行っていると「難しい」「理解できない」という声に出会うことがよくありますが、これは、すでに罠にはまっている状態です。
マネジメントの本質は「理解」ではありません。マネジメントは「行動して成果を出す」ものです。
マネジメントは頭の中で思考実験するのではなく、現実世界に働きかけて、変化を起こさなければ、意味がありません。
実際ドラッカーは、「情報」と「知識」を明確に区別しています。
たとえばこの記事を読んだ段階では、マネジメントのことは、頭の中に記憶された「情報」に過ぎません。
その情報を使って行動を起こし、何らかの変化を得たとき、はじめて情報が「知識」(kmowledge)となります。
『プロが解説する乗馬テクニック』をボロボロになるまで読み込んだ人が、「僕はこんなに勉強したのだから、並み以上に馬を乗りこなせるようになった」(マネジメントできる)と豪語していたら、あなたは本気で大けがを心配するはずです。
ドラッカーを信奉するのではなく、「本当かな?」と疑いつつも、まずは行動してみる。ドラッカーはいうなれば「成果をあげるための道具」なのです。
「実践する習慣」を身に着けるドラッカーの読書会!
わたしたちDラボは、“マネジメントの父”ことピーター・F・ドラッカーの読書会を運営しています。
ドラッカーの読書会は、経営者だけでなく、マネジャーや新人までが、互いの興味・関心・視点での違いを意識しつつ、成果をあげるためのマネジメントを学び合う場です。
この読書会では、ドラッカーを読み込み、実践して、ビジネスで大きな成果をあげています。
この読書会ではアウトプットをとても大事にしています。実際にわたしたちは、この読書会を通じて、「これまで主体性のなかった社員が自発的に提案をしてくれるようになった」「経営者目線で事業のことを真剣に考えてくれるようになった」という事例をたくさんみてきました。
経営に活かした事例ドラッカーの読書会は、経営者と社員が同じ問題意識をもち、同じ目線で学びあえる貴重な機会です。

もしあなたが、「リーダーシップを発揮できない」「資金調達が難しい」「人材育成がうまくいかない」「人材が定着しない」「売上が伸びない」「事業の将来に不安がある」「相談相手がいない」と悩んでいるなら、ぜひ一度、社員と一緒に読書会に来てください。無料体験も実施中です。オンラインで開催しているため、全国の経営者やビジネスマンとつながれる貴重な機会にもなるはず。
はじめて読むドラッカー読書会
 お気に入りに追加
お気に入りに追加Dラボ
当サイトDラボを運営しております。
ドラッカーを学んだ経営者やビジネスマンが実際に仕事や経営に活かして数々のピンチを乗り越え、成功を収めた実例を記事形式で紹介しています。
また、「実践するマネジメント読書会」という、マネジメントを実践的に学び、そして実際の仕事で活かすことを目的とした読書会も行っております。
2003年3月から始まって、これまでに全国で20箇所、計1000回以上開催しており、多くの方にビジネスの場での成果を実感していただいています。
マネジメントを真剣に学んでみたいという方は、ぜひ一度無料体験にご参加ください。
最新記事 by Dラボ (全て見る)
- 【ドラッカーに学ぶ】マネジャーの役割と仕事は?必要なスキル4選を解説。 - 2025年3月26日
- 【ドラッカー流!チーム作りの極意】成果を出す組織が実践するマネジメントの基本。 - 2025年3月20日
- 企業の強みとは何なのか?競合にはない強みの見つけ方とは。 - 2025年3月5日
- なぜ自分の部下は成長しない?上司として伝えたい成長の秘訣7つを徹底解説。 - 2025年2月19日
- 正しい部下の育て方はある?自己成長を促すために必要な7つのポイントを徹底解説。 - 2025年2月5日
 Facebook
Facebook